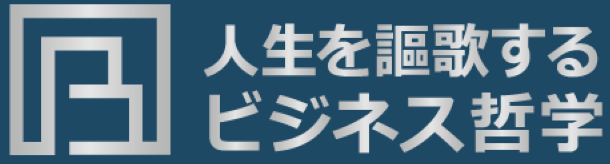私は、2009年に売却する健康食品・化粧品メーカーを、2000年代半ばに創業しました。
当時は、ドラッグストアや量販店などの販売チャネルが中心だったのですが、インターネット通販も行い、顧客からの受注は社内スタッフの業務だったため、多いときで約30名のスタッフが必要でした。
やがて、電話受注も開始したため、人件費を低く抑え、ある程度の質を提供できる中国の大連にあるコールセンター企業に、徐々に機能を移行していきました。
また、製造は日本国内だと価格と質のバランスが悪いため、初めから中国・天津市の工場に委託していました。
こうして、内外価格差によるアービトラージ(裁定取引)がもたらす恩恵が利益にも貢献していました。
社会変化の潮流
それ以降の中国の成長ぶりから、今、中国への外注による同様の恩恵を得ることは難しいでしょう。
もちろん、もっと遠方の、まだ人件費が安い国や地域を探して運営する、という考え方もあります。
しかし、「同業務を安い人件費で成立させるにはどうするか」という問いより、「人を介在させず、業務を自動化、あるいはシステムに組み込めるか」という問いの方が、今後は適切なのかもしれません。
そして、この延長上に、AIがもたらす未来なるものがあるようです。
私自身、AIに関する特段の専門知識を持っているわけではないので、専門家に話を聞いたり、書籍やメディアで見掛ける情報をかじった程度ですが、「多くの業務や職業がAIに代替される」という認識を持っている方は、専門家、一般人を問わず、かなり多くの割合に登っているようです。
さて、2000年代後半から2010年代後半の、ビジネスにおける大きな変化は、以下の3点だと思います。
- 核となる業務以外は、自社での内製から外注へ(海外も含む)
- 所有価値から使用価値へ(民泊やカーシェアで良く聞く言葉ですが、ビジネス用途ではクラウド化が代表例)
- 人からデジタルへの置き換え(延長としてのAI)
1、2は身をもって経験してきましたが、このトレンドは年々進行しております。
さらに、3の「人からデジタルへの置き換え」は、AIサービスが雑誌で特集されるほど、広がりつつあるようです。
AIによる制約条件からの解放
誤解を恐れず申し上げると、上記3つのトレンドを完全に実装してしまえば、「意思決定する人」、「人の感情を動せる人」以外は、汎用化し買い叩かれることになるでしょう。
自動運転に代替される職種はもちろん、介護のような顧客と密接にセッションするような業種もロボットに代替されてしまい、会計士や弁護士のような専門職でさえ人口知能に代替されてしまう、と言われています。
雇用者が守れている日本の法律、心が通う交流の魅力、人間ならではのクリエイティビティなど、一定の緩和となる要素があるのも事実です。
現時点を切り取ると、大きな変化は起きてないと錯覚しますが、決して抗えない変化が動き出し、数年レンジの時系列で見た場合、全く違う日常風景が広がったのを、我々はすでに目撃しています。
インターネットやスマートフォンのように、当初は批判にさらされていた対象が、日常に溶け込み、それまで代替していた商品やサービスが退場していったことは、何よりの証左です。
しかしながら、ドラッカーの言葉から、全く別の見方ができます。
成果をあげる者は、機会を中心に優先順位を決め、他の要素は決定要因ではなく制約要因にすぎないとする。
『経営者の条件』(ドラッカー著、ダイヤモンド社)
重要でないが対応しなければならない仕事が、AIに代替される未来は、制約条件が減っていく未来ということであり、本来集中すべき、成果を上げるための時間が増える、という見方です。
重要なことのみに集中できる環境と社会の到来。
個人のみならず、社会全体としても、価値を産む行動が人間の活動の主となる未来に、期待を抱かずにはいられません。